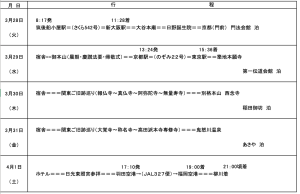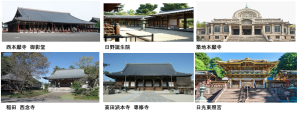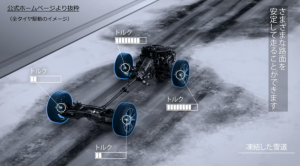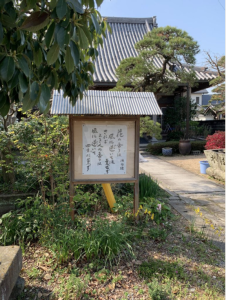中国・上海出身で、日本を拠点に両国を行き来しながら活動していた歌手のamin(アミン)さんが七月二九日、四八歳の若さで亡くなった。死因はがん。突然の訃報に驚き、早過ぎる死を悼みながら彼女との交流を振り返っている。
知り合ったのは二〇一〇年春。彼女は故郷で開かれる上海万博の応援ソング「海を越えるバトン」を歌っていた。万博で行われる日中友好コンサートに同行する前にインタビューした。その澄んだ歌声と誠実な人柄に惚れ、一気に親しくなった。気負うことなく「歌で日中の懸け橋になりたい」と語る笑顔が素敵だった。
アミンさんの本名は巫慧敏(ウー・ホイミン)。お父さんは作曲家、お姉さんは二胡奏者のウェイウェイ・ウーさんという音楽一家に育ち、一三歳でアイドル歌手としてデビュー。透明感あふれる歌声で「天才少女歌手」と呼ばれた。アミンは中国語で「ミンちゃん」の意味。幼いころからの愛称を芸名にした。
一九歳のとき、親しみを感じていた日本の言葉と文化を学ぶため来日。「アイドルではなく、歌手としてもっと活動の場を広げたい」。そんな思いが日本を拠点にする決断につながったという。
〇三年、サントリーウーロン茶のCMソング「大きな河と小さな恋」が二〇万枚を超すヒットとなり、日本でも注目された。〇五年の愛知万博では松任谷由実さんらとユニットを組んでテーマソングを歌った。このユニットはNHK紅白歌合戦に選ばれ、彼女は中国本土出身として初の出場歌手となった。
その後もNHKの中国語講座に出演したり、上海のテレビに出演して日本の唱歌を日本語で歌ったりしながら双方の文化を発信。福岡市在住の中国人男性と結婚し、活動拠点を福岡に移してから一層親しくなり、食事をともにしたり、博多で単独ライブを企画したりする関係だった。そんな交流の中で特に印象に残っているのは「歌で日中の懸け橋になる」という決意を固めたきっかけだった。
「生まれ育った中国と大好きな日本をつなぐ懸け橋になりたいとずっと思ってきましたが、決定的になったのは〇五年春、中国全土で巻き起こった反日デモです。信じられなかった。でも現実として受け入れなければならない。私にできることは歌うこと。歌でメッセージを伝え、喜びや悲しみをハーモニーで包み込み、心の距離を近づける役割を担えたら、お互いに共感できるはずだと思ったんです」
三年前に離婚し、再び拠点を東京に移してからは音信が途切れ、闘病生活のことは全く知らなった。共通の友人によると、離婚後、卵巣がんが発覚。手術後いったんは快方に向かったが、がんの転移が見つかり、最期は上海から呼び寄せた両親と姉に見守られて息を引き取ったという。
元気だったころの笑顔を思い出せば、日本語で包み込むように歌う「故郷」が聞こえる。日本の唱歌の世界を深く理解し、表現した中国人歌手だった。
(TVQ九州放送・傍示文昭)