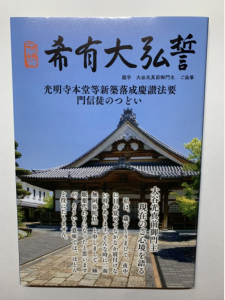一日一生。 光明寺門徒 本多修三
私が18歳の時、父(享年56歳)が他界して
それまで、繊維業を営んでおりましたが
その後、母が経営を引き継ぎ
テナント賃貸の不動産業に事業転換いたしました。
私は、兼ねてからの夢で美大に進学をし卒業後、
東京で広告制作のグラフィックデザイナーの道に進みました。
上京してからは、大手広告代理店からの仕事を請け負う会社で
一途に25年広告デザインに没頭し
結婚し子供も2人授かることができました。
思えば、祖父から父へと受け継がれた財産のおかげと
母と叔父(故)のおかげでまた何不自由なく、
夢に向かって邁進できた東京での25年でした。
母も高齢化し後を引き継ぐため 5年前に
久留米に戻り、事業継承しましたが
東京での、ものづくりの情熱が蘇り
久留米の伝統工芸藍胎漆器を訪ね。
その後、別府で人間国宝の竹細工に出会い衝撃を受け
竹編みの室内タイルを発案し建材開発を発案し起業をしました。
ゼロからの起業のため竹の協力会社を求め
初めは手探りで人の伝手もなく飛び込み営業など
思いつくことはなんでもやってみましたが
そう甘いものではなく、暗中模索の日々が続きました。
その後、あきらめることなく協力者をもとめて
東京・栃木・大分・福岡・福間・八女・大川と訪ね回りました 。
そうしているうちに、一つまた一つと
不思議なご縁の糸がつながりはじめ
丁度、その頃にご住職からお誘いいただき先祖への感謝をこめて
月一のお経を唱えに光明寺さんへお参りに行くようになりました。
ご住職の説法を伺ってとても感銘を受けたお言葉で
一日一生。
「一日を一生のように生きよ、明日はまた新しい人生」
「あせらず、あわてず、あきらめず、無理をしない」
というお言葉が不思議と自分の心のなかで腑に落ち、
そのおかげで当時悶々としていた気持ちの視界がひらけ
一日一日を悔いのない生き方を実践していると
不思議な竹のご縁のつながりが生まれ
竹の事業も少しずつ前進させることができ
その言葉が心の支えとして
今の私の勇気の源になっています。
本多家のルーツは、雲仙市愛野で
向かえには諫早湾 後は雲仙・普賢岳が見える
風光明媚な場所に曽祖父のお墓があります。
不思議とその土地に立つと本多のご先祖様のいぶきと
安心感が湧き立ってきます。
私も気がつけば
今年で54歳、父の他界した年齢に近づき
祖父も49歳で亡くなっているため
この年になり 自分とはなんぞやと自問自答の毎日ですが
阿弥陀さまにおまかせし、先祖に感謝し
挑戦する勇気をいただきながら
一日一日を大切に過ごしています。
(合掌)